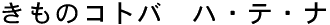|
| 「きもの」には着用する「とき」「ところ」によって様々な種類があります。慶びのとき、楽しみのとき、暑いとき、寒いとき、晴れやかなところ、遊びのところ、寛ぎのところ。それぞれの「とき」と「ところ」にふさわしい「きもの」があります。 |
 |
|
 |
| 「きもの」は繊維製品です。か細い糸を織り上げて布にすることで「きもの」は生まれます。どのような糸を用い、どのように織り上げるか、によって様々な「きもの」の素材が生まれます。 |
 |
|
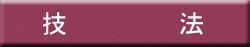 |
| 「きもの」の染め方は大きくふたつに分かれます。布になる前に糸から染める「先染め(さきぞめ)」と、布になった後から染める「後染め(あとぞめ)」です。「先染め」は「織物」、「後染め」は「染物」と大別できますが、染め方、織り方、には様々な染織技法があります。 |
 |
|
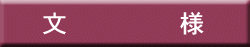 |
| 様々な素材、技法を用いて「きもの」は生まれますが「きもの」に表現される意匠には「きもの」ならではの文様が多くあります。「きもの」に描かれる文様には日本の歴史や文化が色濃く反映しているのです。 |
 |
|
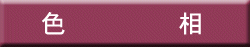 |
| 古今東西、色は命です。しかし、色相も文様と同じく、日本の風土の所産であり、山紫水明の日本の風土から生まれた、日本の色があるのです。そして、それぞれの時代に生きた日本人に、愛され好まれた色も、またあるのです。 |
 |
|
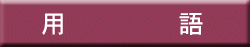 |
| 「きもの」は、古来より日本人が着用した衣服が、時代の変遷と共に変化し、現代の「きもの」に完成したものですので、日本の歴史と伝統によって培われた、「きもの」の創られ方、使われ方があります。、「きもの」独自の用語がある由縁です。 |
 |
|