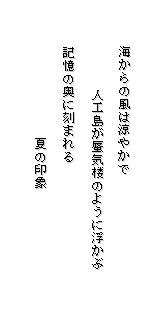 |
 |
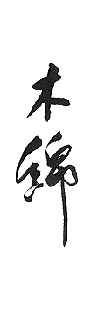 |
『木綿(もめん)』 |
|---|
| 綿の栽培が日本ではじまったのは、室町時代の後期の頃でした。さかのぼること七百年、延歴十八年(七九九)に三河の国の海岸に漂着した崑崙人によって綿の種が持ち込まれ栽培されましたが栽培方法がよくわからず絶えてしまいました。日本各地で本格的に綿の栽培がはじまり、木綿が織りはじめられる江戸時代には、木綿は庶民のきものとして急速に普及します。それまで麻などの木の繊維で織ったゴワゴワした布しか知らなかった庶民にとって、柔らかく、暖かく、肌にそい、何より美しい色に染まる木綿は夢のような布でした。 木綿が急速に普及したのは、木綿が麻とは異なって生産の分業化、商品としての流通が可能であったからです。倹約令により絹ものを身につけることを禁じられた庶民は、木綿のきものに美意識をそそいで久留米絣や唐桟など、農民や町人の生活を彩るきものを作り上げたのです。 木綿の郷愁をさそう素朴で、しかし斬新なきものは今なお作り続けられています。「ゆかた」もその一つですし、「久留米絣」「薩摩絣」などの飛白、「唐桟」や「越後」の縞や格子など、絹のきものとはひと味違ったお洒落が楽しめます。 「もめん」という言葉の由来ですが、江戸時代以前の日本人にとっては「綿(わた)」は蚕の繭を引きのばして作る絹の「真綿(まわた)」を指していました。江戸時代になって日本でも綿花栽培が盛んになり、絹の綿「真綿(まわた)」に対してアオイ科の植物「綿」から作られる綿を「木綿(きわた)」と呼びました。「木綿(きわた)」を音読みすると「もくめん」、それが「もめん」になまったと思われます。 |
 |
|---|