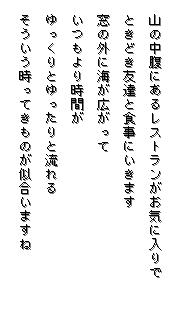 |
 |
 |
『縞(しま)』 |
|---|
| 織で模様を表現するもっとも原初的な技法が縞です。一定間隔で異なる色糸を織り込むと縞になります。どのような色糸を組み合わせるのか、間隔をどうあけて織るかによって縞模様は単純でありながら無限に変化します。 日本の染織史上縞が広く普及したのは江戸時代のことです。室町時代末期、南蛮船の渡来による交易によってインドや中国の染織品が国内にもたらされました。なかでも当時筋(すじ)と呼ばれていた縞模様の織物はあざやかな色彩と大胆な構図で日本人を魅了しました。南方から持ち込まれたこの織物は「島渡りの布」ということから「島物」と称され、「縞(島)」と呼ばれるようになりました。因みに「島物」は当初織物だけを指したのではなく南蛮船が運んできた珍しい品物はすべて「島物」と呼ばれました。明治以降外国製品を「舶来品」と称したのと同様です。「縞」という文字は元来中国では「上等の白生地」を意味し高級品という雰囲気でこの文字が用いられるようになりました。 江戸時代、舶来品として珍重された縞は幕府の度重なる奢侈禁止令により華美な服装を禁じられた庶民によってその渋さのなかに秘められた研ぎ澄まされた感覚が粋としておおいにもてはやされました。単純な幾何模様であるがゆえに、いつの時代にあっても先端的なファション性を失いません。 |
 |
|---|