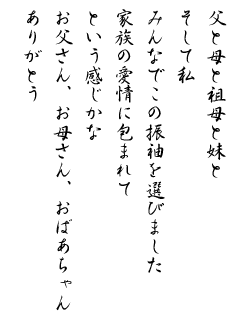 |
 |
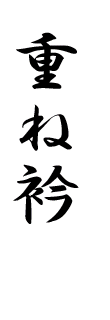 |
『重ね衿(かさねえり)』 |
|---|
| 目は口ほどにものを言う、とか。さすれば着物の襟元もそれなりにお洒落のポイント。その昔「えり何々」という衿の専門店が全国各地にあって、たとえばかの有名な京都の「ゑり善」さんは夏目漱石の小説にも登場する老舗中の老舗の呉服屋さんですが元々は衿の専門店でした。 |
『半衿』 |
|---|
| 半衿は襦袢の本衿に付ける掛け衿です。本衿のほぼ半分の長さであることから半衿と呼ばれた、とも、半幅の布を掛け衿に用いるため、とも言われています。江戸時代には表着にも半衿が付けられていたそうです。衿元を美しく見せる、という意味でもっとも重要なポイントですので色々な半衿があります。塩瀬の白生地の半衿が一般的ですが、縮緬や綸子の白生地、また色衿のほか小紋柄もあります。そのほか刺繍衿、など種々様々な素材、加工の半衿があります。過日、弊店で開催された能装束展では唐織の半衿が販売されました。 |
『広衿・バチ衿』 |
|---|
| 着物と襦袢の衿を仕立てする方法に「広衿」と「バチ衿」があります。「広衿」はその名の通り「衿裏」を付けて幅広く仕立てをします。着用時には背筋の衿付で真二ツに折って固定します。固定する方法には現在一般的な「ホック止メ」というホックを使用する方法と「糸止メ」という糸でくくる方法があります。「バチ衿」は仕立ての段階で二ツに折って仕立てます。「バチ衿」と名付けられたのは背筋の衿付で衿巾が一寸五分、衿先で二寸で仕立てをしますので衿付から衿先にかけて次第に幅広くなりその形が三味線の「バチ」に似ているからです。ちなみに普通、着物は「広衿」、襦袢は「バチ衿」が多いですが、着物でも「バチ衿」、襦袢でも「広衿」になさる方もおられます。「バチ衿」は着用時、衿を二ツに折る手間がかからないので簡便であること、「広衿」は衿の間に衿芯を入れて衿の形を整えたりできますので、「広衿」「バチ衿」それぞれの使いこなしがあるからです。 |
『重ね衿・伊達衿』 |
|---|
| 平安時代の十二単衣は何枚も着物を重ねて着用し、衿元、袖口、裾などにそれぞれの着物の色が重なる美しさを愛でる美意識がありました。それは今も脈々と受け継がれて、着物の八掛の色合わせに生かされているのですが、さらに着物と襦袢の衿元の間にあたかももう一枚の着物の衿があるように重ねられるのが「重ね衿」です。生地は紋綸子や一越縮緬を無地染したものが多く用いられます。また「伊達衿」とも呼ばれますが、本来の機能があるわけではなく、あくまでお洒落のために用いられることからそう名付けられています。 |
 |
|---|