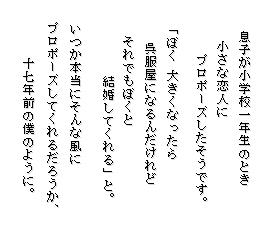 |
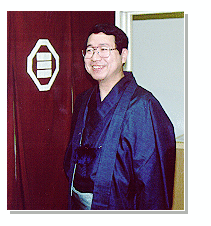 |
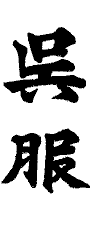 |
『呉服(ごふく)』 |
|---|
| 「日本書記」に雄略天皇の時代、呉と呼ばれた揚子江下流の国に使者を送り呉服を招いた、という記述があります。 「呉服」とは絹を作る人々のことで、日本では「くれはとり」と呼ばれていました。 「くれ」とは「日暮れ」からきた語で、中国が日の沈む方角に位置することから名づけられました。「はとり」は「はたおり」がつまって出来た語で、「呉服(くれはとり)」とは中国から渡来した機織り技術者のことでした。 やがて「呉服(くれはとり)」が作る絹の衣服も「くれはとり」と呼ばれるようになりました。しかし「くれはとり」とは呼びにくいので、奈良時代にはそれを音読みで「ごふく」と呼ぶようになりました。 以来、絹の衣服「きもの」は「呉服(ごふく)」、それを商いする私どもは「呉服屋」となりました。 |
 |
|---|