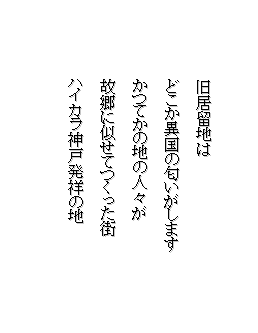 |
 |
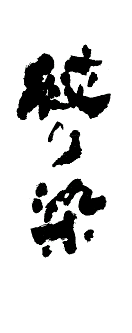 |
『絞り染』 |
|---|
| 絞り染は布地を括って染めるという単純な技法ゆえに世界各地で自然発生的に生まれました。わが国でも古くから原始的な絞り染が行われておりましたが、奈良時代には多種多様な技法が生み出され 美しい絞り染が正倉院に残されています。平安時代、川面に紅葉が流されてゆくさまを絞り染になぞられた「ちはやふる 神代もきかず 立田川 からくれないに 水くくるとは」と百人一首に歌われたように絞り染はますます盛んになりました。室町時代には幻の「辻が花染」、江戸時代には「鹿の子絞」と 絞り染は、その素朴さと華麗さとが日本人に愛されつづけてきたのです。 |
| 疋田絞 爪先で布地をつまみ 絞り目を一粒づつ絹糸で三回ないし七回括る。綺麗な絞り目で模様の面をつくります。 |
| 一目絞 爪先で絹糸をニ回強く巻締めて括る。模様の線を表現する。 |
| 縫締絞 布地に綿糸で平縫いし、糸を引き締めるもので 糸の縫い入れ方により色々の技法があります。 |
| 針疋田絞 疋田絞がすべて手絞りであるのに対し、爪先で布地の絞り目をつまむ代りに、絞り台の針先に引っかけ、綿糸で括るもので三回ないし五回括ります。 |
| 針一目絞 針疋田絞と同様に、手で絞り目をつまむ代りに絞り台の針先に引っかけて、ニ回綿糸で括ります。 |
| 桶絞 桶絞は防染する部分を桶の中に入れ、染色する部分だけを桶の縁に出して強く締めつけます。 |
| 帽子絞 帽子絞は防染する部分をビニールで包み、その上から強く糸で締める技法です。 |
 |
|---|