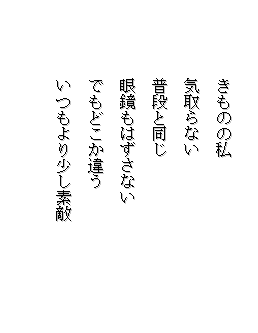 |
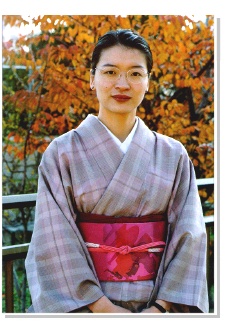 |
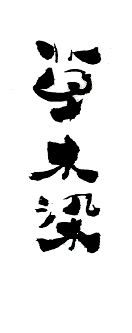 |
『草木染』 |
|---|
| 草や木を布に摺りつけて色を染める、染織の歴史はそこから始まりました。そして人類は、より鮮やかな、より強い色を求めて工夫を重ね、植物や動物、また岩石など様々な染料の素材を開拓し、媒染剤による発色と固着の方法を発見しました。 しかし化学染料が発明され、より早く、より多く、より簡単に染色が可能になると、二千年以上もの古い時代から行われてきた天然染料による染色は、たちまちのうちに衰退しました。 けれども化学染料では出しえない、深味、滋味のある色を追い求める人達が天然染料による染色技術を受け継ぎ、手間ひまを惜しまない創作を続けています。そうして作り出される染織品は、いつしか草木染と呼ばれるようになりました。 |
| 風土の色、日本の色 藍色、茜色、小豆色、亜麻色、杏色、桜色、菖蒲色、蘇芳、菫色、丁子色、茄子紺、藤色、牡丹色、桃色、山吹色、若竹色。色の呼び方には自然の植物がそのままあてられています。鴇色、鳶色、鼠色、鶸色など動物の名前、黄土色、金色、銀色、鉄色、鉛色など岩石、鉱物も色の呼び名に使われています。 草木染は、それら自然にあるもの、おおくは野山に自生する植物の葉、樹皮幹の材、そして花を、実を、根を染料としています。草木染で染め上げられた色が優しく心をなごませるのは、目に親しい身近な自然がそのまま色になっているからです。 日本の風土に生まれ育てられた色、それは日本の伝統の色となり、私達の心にもしみとおるのです。 |
| 色が生きている 草木染の色はなぜ奥行きがあるのでしょう。草木染は自然の植物などを染料とする有機染色です。ひとつの染料のなかにはさまざまな色素が含まれていて媒染剤によってまったく違った発色をします。草木染の深い色相は、発色した色素以外の色素が、表面の色彩の背後に含まれているからです。 また染め上った状態では、色素はすべて発色しきってはいませんので日が経つにつれ徐々に発色し鮮やかさを増します。 |
| 手作りの色 草木染は制作過程でたいへんな手間を必要とします。原料の採取から乾燥などの処理、そして染料を作り染めるなど、一貫して人の手をわずらわさなければなりません。機械化されている部分はほとんどないといっていいでしょう。私達を魅了してやまない草木染の色相は、製作者が丹精こめて染め上げた手作りの色なのです。 |
 |
|---|