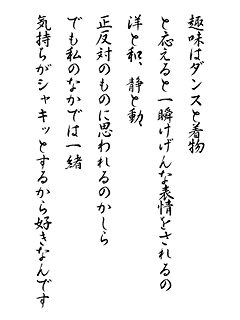 |
 |
 |
『八掛(はっかけ)』 |
|---|
十数年前、会計の帳簿の手伝いに来てくれていた女子大生が伝票を見ながら「ハチカケって何ですか」と聞かれて「ハッカケと言って着物の裏地のこと」と答えたのですが、さて何で着物の裏地が八掛なのか、とあらためて考えたら分からない。八掛どころか呉服屋なのになぜ着物が呉服なのかも良く知らない、ということにハタと気がつきました。我が身の為、と思って調べてみようと考えたのが「きものコトバ ハ・テ・ナ」の始まりです。さて何で着物の裏地を八掛(ハッカケ)と呼ぶのでしょう。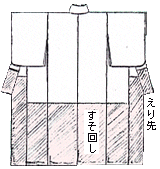 女性の着物の裏地は上半分が白の胴裏、下半分は色の八掛が付けられています。着物の裏側の図で色に塗られた部分が八掛で右図のように八枚の布地に分かれています。それが八掛の由来です。「八」は布地の枚数、「掛」は表地に付けられている、という意味でしょう。ちなみに現在はほとんど白色しかない胴裏は昔は紅絹(もみ)といって鮮やかな緋色もありましたし三十年ほど前までは朱鷺色(ときいろ)といってピンク色の胴裏もよく用いられていました。いつの頃からか白色だけになってしまいましたが少し寂しい気もいたします。
女性の着物の裏地は上半分が白の胴裏、下半分は色の八掛が付けられています。着物の裏側の図で色に塗られた部分が八掛で右図のように八枚の布地に分かれています。それが八掛の由来です。「八」は布地の枚数、「掛」は表地に付けられている、という意味でしょう。ちなみに現在はほとんど白色しかない胴裏は昔は紅絹(もみ)といって鮮やかな緋色もありましたし三十年ほど前までは朱鷺色(ときいろ)といってピンク色の胴裏もよく用いられていました。いつの頃からか白色だけになってしまいましたが少し寂しい気もいたします。 |
 |
|---|