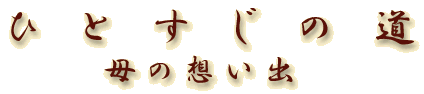
第十章 晩 年 |
|
|---|---|
母の退院が近づいた頃、主治医の松田たかのり先生から、母の退院後の生活について、様々な助言を頂戴しました。現在の日本では、介護制度が整備されているので、介護制度を十分に活用されるように、というご助言でした。退院後、ケアーマネージャーさんのご指導で、デイサービス、ショートステー、訪問看護、往診、など、様々な介護支援を頂戴しました。私は、つくづく、介護制度が整備された時代に、母の世話をすることになって良かった、と思いました。母に残された人生、母の余生を、母が大好きな、須磨の自宅で過ごせることが、私たち、4人の子供の、共通した願いだったから。 退院して、自宅に帰った母は、住み慣れた自宅に、心が落ち着いたのか、入院していた時より、以前の母に、少し戻ったようでした。しかし、すでに、89歳を過ぎて、次第次第に、気力、体力が衰えていきました。自分のことは自分でする、ことを何よの矜持にしていた母ですが、次第に、そのことが難しくなっていきました。家内は、母が出来なくなったことを、母に代わってするようになりました。そして、家内がすることは、次第に多くなっていきました。 「丸太や」は、平成16年に社員の谷口澄治さんが亡くなり、私たち夫婦だけの商売になりました。「丸太や」の商売にとって、家内は欠かせない存在です。同時に、母にとっても、今まで以上に、欠かせない存在になりました。家内の、精神的、肉体的負担は、一挙に増しました。何処まで、その負担に耐えられるのだろう。不安でした。しかし、家内は、最後の最後まで、母を自宅で見守る決意を固めました。それは、家内の信念だった。人間の一生の、最後の終わり方の。 平成21年1月9日、未明、母 三木キクヱ、は亡くなりました。93歳、あと7日で誕生日を迎えると、94歳になるところでした。毎日、夜中の2時から3時に間に、母の様子を見に行くことが、家内の日課でした。9日の2時半ごろ、いつものように母の様子を見に行って、異変に気付きました。すぐに、寝入っていた私を起こして、「お母さんの様子が普通じゃない。息をしていない」。私も、すぐ起き上がって、母の枕元に立ち、母の口や鼻に顔を近づけましたが、何も感じるものがありません。手は、まだぬくもりがあって、家内は、人工呼吸と心臓マッサージを施しました。もしかしたら、と救急車を呼び、病院に搬送していただきましたが、3時51分、先生が、「残念ですが、これ以上、処置を続けても仕方が在りませんので」、と伝えられました。老衰による死亡でした。 家内に起こされて、母の様子を見た私は、その表情が、とても穏やかなのに救われました。静かに、眠りにつくように、息を引き取ったのだ。まさに、最後の息を、引き取った。私は、母の姿に、一本の蝋燭が、生命の炎をともし続け、最後の |
 |
 |