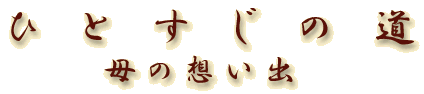
終 章 釋宝寿 |
|
|---|---|
母は、一本の樹だった。背の高い樹でも、幹の太い樹でも、枝振りの大きな樹でも、なかった。唯、大地に深く根を降ろした樹だった。大風に倒れることも、長雨に腐ることも、日照りに枯れることも、なかった。小さな花を咲かせ、小さな実を結び、新たな種を、大地に蒔いた。私たち、子供は、孫は、ひ孫は、その樹に守られて、大きくなった。「丸太や」、もまた。樹に樹齢があるように、母も年輪を重ねた。「93」、の。もう少しで、「94」、を数える時、樹齢は尽きた。樹齢が尽きた樹が、朽ち果てて、土に帰るように、母も、土に帰った。 母は、「四」、という数字と、「九」、という数字を、忌み嫌った。「四」、は、「死」、を、「九」、は、「苦」、を連想させるから。長男、次男の、「死」。夫の、「死」。叔父の、「死」。母は、「苦」るしい、「死」に、幾つも、立ち会った。その、「死」、は、決して、許されない、認められない、「死」、だった。だから、「寿」、という字が好きだった。「寿―いのちながし」。事あるごとに、「寿」、という字を書いていました。賀状に始まって、一年の間、何度も。「命」を永らえること、その、祈りにも似た気持ちが、母に、「寿」、という字を書かせた。呪文のように。 母が亡くなって、枕経を唱えにお越しくださったお坊様が、「もし、お好きな言葉があれば、法名にお入れいたします」、とおっしゃってくださったので、「母は、『寿』、という字が大好きでしたので、もしお入れいただければ」、とお答えしました。お通夜の日、式場で、初めて眼にした、母の法名は、「釋宝寿」。「命」を「宝」にすることが「幸」である。私は、そう読みました。これほど、母の、母の生涯に相応しい名前はありません。 |
 母自筆の「寿」 |