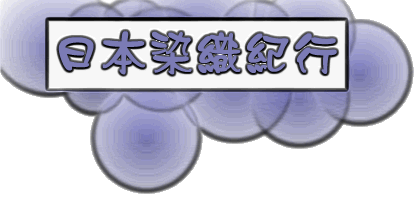| 沖縄−芭蕉布 | |
 カメラに残っていたフィルムをやっと撮り切って出来上がった写真、
沖縄を旅行し芭蕉布の里−大宜味村喜如嘉(おおぎみそんきじょか)
を訊ねて平良敏子(たいらとしこ)さんに親しくお話を聞かせていただいた別れ際、
いっしょに並んで撮っていただいた写真、
その写真を見た途端まるで昨日のことのように想い出すのです。
平良敏子さん、という芭蕉布を織ることに一生を捧げてこられた方の、
人生の厚み、重みに圧倒されたことを。
カメラに残っていたフィルムをやっと撮り切って出来上がった写真、
沖縄を旅行し芭蕉布の里−大宜味村喜如嘉(おおぎみそんきじょか)
を訊ねて平良敏子(たいらとしこ)さんに親しくお話を聞かせていただいた別れ際、
いっしょに並んで撮っていただいた写真、
その写真を見た途端まるで昨日のことのように想い出すのです。
平良敏子さん、という芭蕉布を織ることに一生を捧げてこられた方の、
人生の厚み、重みに圧倒されたことを。六月も二十日過ぎ、 梅雨明け間近な沖縄は時々雨が落ちてくるあいにくの空模様でした。 平良敏子さんの工房、芭蕉布織物研究所を訪れ、 一階でビデオを見せていただいたあと二階の工房で見学していると、 初老の上品な女性が「どうも遠いところを」 と笑みを浮かべて近づいてこられました。 ひと目で平良敏子さんその人だと分かりましたが、 お年を召されているであろうにとても俊敏な身のこなしが印象的でした。 (後日資料を見せていただいたらなんと七十九才! まったく信じがたいことです。) あいさつもそこそこに芭蕉布づくりについて、 芭蕉の木を育てること、その幹から糸をとること、 染めて織り布に仕上げるまでのすべてを予備知識のないものにも分かりやすく丁寧にお 話して下さいました。 その言葉のはしばしにみなぎる力、 眼の輝きは知りつくした芭蕉布の魅力、 芭蕉布づくりの労苦や充足を語りつくしたい、 伝えたいという思いのなせるところなのでしょう。 平良敏子さんは「芭蕉布は身にそわないきものですから」 と何度も繰り返しおっしゃいました。 もとはといえば木、絹や木綿の柔らかさ、 しなやかさを求めるべくもない、固い、ゴワゴワした素材。 しかし暑い夏を過ごさねばならない沖縄の地にあってはこれ程しのぎやすいきものはあ りません。 身に添いにくい素材だからこそなんとか膚に添うように、 より細く均質な糸づくりに励まれたのでしょう。 しかし糸が細くなればなる程それを染めることも織ることもさらに困難になります。 しかし身に添うきものをつくるために平良さんは知恵と力をつくしてこられたのです。 工房にはたくさんの女性が仕事をされていました。 「芭蕉布は女性が作ってこられたのですか」という問いかけに 「ずっと昔からそうです。男のかせぎにはなりませんから」 そうかこれだけの労苦が報われるだけの収入にはならないのだ、 今も昔も、と気づきました。 |
 |
|---|