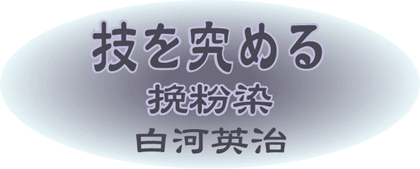
|
|
夏の終わり、葉書が届きました。白河さんが京都のギャラリーで個展をされるという案内です。初めて見せていただいた作品は、 まっすぐ前をみつめる白河さんのまなざしが捉えた『表現』でした。「親父が型染の職人やったから小さいときから染の手伝いをしてました。 今も仕事としてはきものや帯を作っているんやけど美術展に出品する作品も作ってます。最近、また無性にきものが作りとなって、きものは女性を美しく見せるものでしょ。 きものが消えて『綺麗な女性(ひと)やな』という印象だけが残るきものをつくりたいんです。」そう語る人のきものを見せていただきたくて、弊店で個展をされるようにお願いしました。 「来年の春ぐらいやったら」 五月の後半に弊店で個展をしていただくことになり三月二日、太秦(うずまさ)(映画村が近くにあります)の工房をたずねました。マッキントッシュのパソコンがあって。「これからはこういうのも使いこなせんと」。 大作の屏風や染額を次々と見せてくださいましたが、圧巻はきものと帯でした。生地全体に撒糊(まきのり)や蝋纈(ろうけつ)のたたきでもない独特のまだら模様があります。 「挽粉染(ひっこぞめ)です。天目染(てんもくぞめ)とも言うけど。長いこと研究したんですよ。これが出来るのは僕だけ。皆んな真似したんやけど誰もものに出来んかった。 そのかわりエライお金使うたから貧乏になりました。」 「工場も見はりますか。吉祥院にあるんやけど。」太秦(うずまさ)から吉祥院へ車で三十分、京都の西入口、桂川にかかる久世橋のたもと近くにありました。 岩手にあった小学校の講堂を移築したという木造の建物が染工場、「挽粉染(ひっこぞめ)を見せますわ。仕事にかかるとピーんと張り詰めた空気になるんです。 それまで職人同志、冗談を飛ばしあってても、始めた途端黙りこんで、そら真剣です。」と下ごしらえ(地入れ)の出来た生地に刷毛で染料をのせていく、 上下をボカシで染め別け、それから大量のおがくずを生地の上に降りかけ、ガスバーナーで下から乾燥させる。手順はキビキビと無駄が無い。 バーナーを止めてしばらくしておがくずをはき落とすと繊細微妙な斑点が浮かび上がっている。「職人以外で工場に人を入れたのは初めてです。企業秘密やから。 おがくずもしっとりしめっているでしょ。薬品をしませているんです。」中に入ったとき鼻をついたのはその薬品なのだろうか。実に百聞は一見に如かず、職人の技に圧倒されました。 「作品がほぼ出来上がりました。」という連絡をいただいて五月一日、ふたたび工房を訪れました。山葡萄のきもの、川面に花びらが浮かぶ帯、挽粉染(ひっこぞめ)の豊な陰影を背景に描かれた絵模様、 「せっかく神戸で開く個展やから神戸の風景を描きました」という訪問着、透明で柔和な神戸の空の下、美しく広がる六甲の山並み、その裾に点在する人家、「京都の山と違って優しいところが大好きや」 という白河さんの気持ちが素直にきものになっています。「個展の期間中はずっと会場につめます。それが来られた方への何よりの礼儀やから」。律儀な人柄とあらためて感心しました。 五月二十三日(木)から二十八日(火)までの会期中、是非白河さんのお人柄と何より作品に触れていただきたいという思いでいっぱいです。 |
|---|

