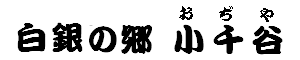 |
|---|
 去る2月27日、新潟県は小千谷市へ、樋口隆司さんの工房を訪ねました。心配していた天気もこの日は何とか持ちこたえ、寒さもひと段落した過ごしやすい気候でした。 去る2月27日、新潟県は小千谷市へ、樋口隆司さんの工房を訪ねました。心配していた天気もこの日は何とか持ちこたえ、寒さもひと段落した過ごしやすい気候でした。朝6時10分発の新幹線に乗って約5時間、長岡駅に降り立つと、改札で樋口隆司さんの奥様が着物姿で迎えてくださいました。オフホワイトを基調とした、柔らかな雰囲気の紬ちりめんの着物です。 長岡駅から小千谷に移動して名物の「へぎそば」をいただいた後、樋口さんの工房を見学させていただきました。実は、私は過去に樋口さんの工房をお訪ねしたことがあります。15年も前のことです。小学2年生の頃のことですので、殆ど覚えていないと思っていました。しかし、入り口の階段を上ると、不思議と15年前の自分に戻るのです。この階段を上ったという記憶、周りに積もった雪をゴジラの真似をして蹴散らした記憶、柱の色、天井の高さ…長い年月を経て蘇った記憶に驚きつつ、応接間へ案内していただきました。 応接間では樋口さんの作品の数々を見せていただきました。袷、単向きの紬ちりめん、単から夏にかけての湯揉み絹縮、そして盛夏の主役、小千谷縮。樋口さんの織物は、色も柄も非常に抑制されている感があります。だから、生地の風合いが、絣という技法の表情が、一つ一つの柄の意味が、自然に浮かび上がってくるのです。   工房を一通り案内していただいた後、今回の最大の目的、小千谷縮の雪晒しを見に行きました。織りあがった反物を雪の上に晒すのです。こうすると、雪が解けたときに発生するオゾンの影響で不純物が取り除かれ、色が鮮やかになり、生地もやわらかくなるのだそうです。天候に左右される作業で、以前社長が小千谷へ行ったときは、悪天候のために雪晒しを見ることができなかったそうです。今回は天候に恵まれ、雪晒しを見学することができました。一般人も雪晒しを体験できるという会場へ行くと、真っ白な雪原の上に何反もの小千谷縮が広げられていました。こうして雪に晒すことを1週間ほど続けるのだそうです。体験もできるということなので、他のお客さんに混じって私も雪晒しに挑戦してみました。 工房を一通り案内していただいた後、今回の最大の目的、小千谷縮の雪晒しを見に行きました。織りあがった反物を雪の上に晒すのです。こうすると、雪が解けたときに発生するオゾンの影響で不純物が取り除かれ、色が鮮やかになり、生地もやわらかくなるのだそうです。天候に左右される作業で、以前社長が小千谷へ行ったときは、悪天候のために雪晒しを見ることができなかったそうです。今回は天候に恵まれ、雪晒しを見学することができました。一般人も雪晒しを体験できるという会場へ行くと、真っ白な雪原の上に何反もの小千谷縮が広げられていました。こうして雪に晒すことを1週間ほど続けるのだそうです。体験もできるということなので、他のお客さんに混じって私も雪晒しに挑戦してみました。小千谷縮は昨年、日本の染織品で始めてユネスコ無形文化遺産に登録されました。一人の人間の中ですら、一つのことをずっと絶やさず続けていくことは困難なことです。小千谷縮が何百年という時間を越えてなお伝え続けられているのは、いつの時代も人々に必要とされる高い品質の製品を世に送り続けた小千谷の人々の努力があったからです。ところで、今回初めて知ったのですが、小千谷縮とここ兵庫は以外な繋がりがあります。というのも、小千谷縮を発明した人が播磨国明石出身の人なのです。小千谷と兵庫、遠く離れた地を結ぶ伝統工芸品、小千谷縮。帰りの新幹線の窓から流れる景色を見ながら、電車もない時代にこの道のりを越えて小千谷へ赴き、何百年も伝え続けられる伝統工芸品を生み出した人がいたのだと思うと、遠い雪国も身近に感じられるように思いました。 |
 |
